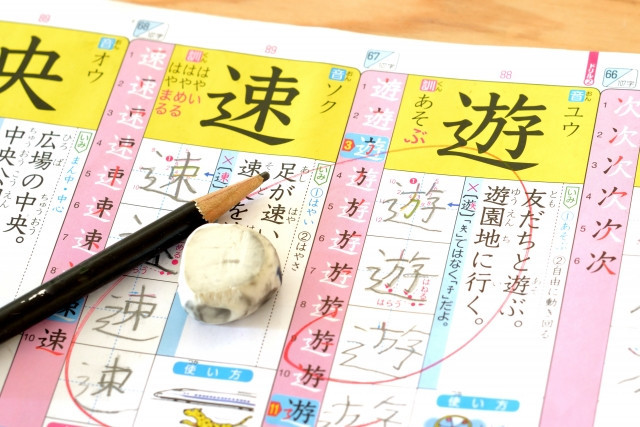文法とは、文を作るうえでの決まりのことです。日本語の細かい文法を知らなくても、意思疎通はある程度できます。しかし、ビジネスメールや正式な書類を書く際は文法の正しい知識が必要です。このコラムでは、日本語の文法について、品詞の意味や用法、表現を詳しく解説します。また、間違いやすい表現や学習者にとって難しいとされている敬語も紹介。日本語の文法について理解を深め、日本語学習に役立てましょう。
目次
- 日本語の文法とはどのようなもの?
- 日本語の文法の基本
- 日本語の文の種類と特徴
- 日本語の文法【動詞】
- 日本語の文法【い形容詞・な形容詞】
- 日本語の文法【表現】
- 日本語の文法【敬語】
- 改めてチェックしておきたい日本語の文法
- 日本語の文法を理解するには
- まとめ
日本語の文法とはどのようなもの?

文法とは、文章を構成するうえでの決まりや書き方のことをいいます。日本語は、主語 (Subject)・目的語 (Object)・ 動詞 (Verb)の語順をとるSOV型が基本です。とはいえ、日本語会話ではときに主語を省略したり語順を変えたりするため、学習者には文法構造が分かりにくく感じることも。細かい決まりを覚えていなくても、日本語での会話は可能です。しかし、ビジネスシーンでのやりとりや公的な書類の提出では、正確な日本語を求められるでしょう。文法に誤りがあると、受け取り手に違和感を与えたり意図が正しく伝わらなかったりと、さまざまな不都合が生じます。そのため、自分の意見や気持ちを正確に伝え、より円滑なコミュニケーションをとるためにも、正しい文法を理解しておきましょう。
日本語の特徴について詳しく知りたい方は、「日本語の特徴とは?文法や漢字など言語学習において難しいポイントを解説」のコラムを参考にしてください。
ピックアップ記事
日本語の文法の基本

日本語の文法を身に付けるには、「言葉の単位」や「文の成分」などの正しい理解が必要です。ここでは、日本語の文法の基本を解説します。
言葉の単位【文章・段落・文・文節・単語】
日本語は、大きい順に「文章」「段落」「文」「文節」「単語」の5つの単位で構成されています。それぞれの「言葉の単位」の定義は、以下のとおりです。
- 文章:言葉のまとまり全体(小説、記事など)
- 段落:長い文章を内容ごとに区切ってできたまとまり
- 文:句点から句点までのまとまった内容の文字列
- 文節:言葉の意味が通るように文を区切ってできたまとまり
- 単語:意味を持つ言葉の最小単位
中でも「文節」は、日本語を正しく理解する際に重要な言葉の単位です。「文節」ごとに区切る際は、文の終わりに付けて感嘆や強調などの意味を添える「ね」を入れても違和感がない箇所で区切ります。以下は例文です。
「毎日、僕は朝早く起きて学校へ行きます。」→「毎日(ね)、/僕は(ね)/朝早く(ね)/起きて(ね)/学校へ(ね)/行きます(ね)。」
文節に区切ることで一文が細かく分けられ、文法構造を理解しやすくなります。
文の成分【主語・述語・修飾語・接続語・独立語】

「文の成分」とは文節を役割によって区別した名称の総称で、「主語」「述語」「修飾語」「接続語」「独立語」があります。5つの「文の成分」の役割は、以下のとおりです。
- 主語:「誰が」「何が」を表す文節
- 述語:「どうする」「どんなだ」など、主語を説明する文節
- 修飾語:ほかの文節の内容を説明する文節
- 接続語:「また」「しかし」「~だから」など、前後の文を繋ぐ文節
- 独立語:ほかの文節と関係がなく独立しており、「ええ」「あら」といった感動や驚きなどを表現する文節
文の成分の順番は、「主語」のあとに「述語」がくるのが一般的です。「修飾語」は詳しく説明したい文節の前に、「接続語」は繋ぎたい文や文節の間に置かれます。「独立語」は文の最初、もしくは最後にくる場合がほとんどです。
各文の成分が複数の文節でできているときは、それぞれ「主部」「述部」「修飾部」「接続部」「独立部」と表します。たとえば、「赤い風船が飛んでいた」という文章は、「赤い」と「風船が」の2つの文節からなる「赤い風船が」が「主部」です。「飛んでいた」は、「飛んで」と「いた」の2つの文節で構成されているため、「飛んでいた」が「述部」になります。
品詞【自立語と付属語】
品詞とは、単語が持つ役割を分類ごとに分けたものです。日本語の文法には、「名詞」「副詞」「接続詞」「連体詞」「感動詞」「動詞」「形容詞」「形容動詞」「助詞」「助動詞」の10種類の品詞があります。
品詞の分類を考える際は、文を単語ごとに分けてその単語だけで意味が通じるかどうかを判断しましょう。一つの単語だけで意味が通じるものを「自立語」、一つの単語では意味が通じないものを「付属語」といいます。
たとえば、「私」や「明日」は一つの単語だけで意味が通じるため「自立語」です。一方、「が」や「で」はほかの単語と繋げないと意味が通じないため、「付属語」に分類されます。品詞を「自立語」と「付属語」、「活用の有無」でまとめると、以下の4つに分類可能です。
【自立語(活用がないもの)】
- 名詞:「私」「車」など名称を表す品詞
- 副詞:「よく」「しっかり」など、ほかの言葉の意味を説明する品詞
- 接続詞:「また」「しかし」など前後の文を繋ぐ品詞(単独で接続語として使われる)
- 連体詞:「この」「大きな」など名詞の詳細を説明する品詞
- 感動詞:「さあ」「あら」など呼びかけや感動、応答を表す品詞
【自立語(活用があるもの)】
- 動詞:「食べる」「歩く」など、動作や状態を表す品詞(う段で終わる)
- 形容詞:「美しい」「美味しい」など、物事の状態を表す品詞(言い切る場合に「い」で終わる)
- 形容動詞:「安全だ」「きれいだ」など、物事の状態を表す品詞(言い切る場合に「だ」で終わる)
【付属語(活用がないもの)】
- 助詞:「に」「で」など名詞に付属して、主語や述語を補う補語になる品詞
【付属語(活用があるもの)】
- 助動詞:「れる」「ない」など、名詞や動詞、形容詞に付属して意味を添える品詞
品詞の一部は、主語と述語のどちらになるかで「体言」と「用言」に区別されます。「体言」は主語になれる「名詞」のこと、「用言」は述語になれる「動詞」「形容詞」「形容動詞」のことです。
区切り符号【。、など】

区切り符号とは、文を見やすくするために付ける記号のことです。適切な位置に区切り符号を付けなければ、読みにくかったり文の意味が変わってしまったりします。日本語の主な区切り符号は、以下のとおりです。
| 区切り符号の名称 | 区切り符号 | 意味や役割 |
| 句点(くてん) | 。 | 文の最後に付ける |
| 読点(とうてん) | 、 | 文中の意味が切れる箇所に付ける |
| かっこ | () | 特定の文字列を囲ってほかと区別させる |
| 中点(なかてん) | ・ | 同種の内容を並べる際に使う |
| 3点リーダー | … | 文頭や文末に付けて余韻を表現したり 単体で沈黙を表したりする |
| 感嘆符(かんたんふ) | ! | 感動を表現したいときに文末に付ける |
| 疑問符(ぎもんふ) | ? | 疑問を表したいときに文末に付ける |
日本語の文章中に必ず使われる「句点(。)」や「読点(、)」のことを「句読点(くとうてん)」といいます。句読点がなければ、区切りが分からず読みにくい文章となるため、日本語の文章を書くときは必ず使うようにしましょう。
日本語の文の種類と特徴

文の意味や構造の違いを表す言葉が、「意味上の文」と「構造上の文」です。ここでは、意味上の文と構造上の文について解説します。
意味上の文
「意味上の文」の種類には、「疑問文」「命令文」「感動文」「平叙文(へいじょぶん)」があります。それぞれの文の意味は以下のとおりです。
- 疑問文:「今日は何をしますか」「好きな色は何ですか」などの疑問を述べる文(文末が「か」で終わる)
- 命令文:「早く支度してください」「静かにしなさい」など、命令や禁止の意味を表す文
- 感動文:「あら、きれいな花が咲いている」「なんて面白いのだろう」など、感動を表す文
- 平叙文:「私はこの学校の卒業生だ」「明日は雨が降る」など、断定や推量を表す文
文の意味や内容を理解できれば、「疑問文」「命令文」「感動文」「平叙文」のどれに該当するかの区別は簡単でしょう。
構造上の文
「構造上の文」の種類には「単文」「重文」「複文」があります。それぞれの文の意味は以下のとおりです。
- 単文:「私は飛行機に乗ります」「明日は晴れます」など、主語と述語が一つだけ使われている文
- 重文:「見た目が良く、性格も良い」「母は看護師で、父は医者だ」など、対等な関係の単文が並んでいる文
- 複文:「明日は雨なので、遠足は中止です」「体調が悪いので、学校を休みます」など、原因と結果といった対等でない関係の単文が並んでいる文
「重文」と「複文」は、前後の文を入れ替えても意味が通じるかどうかで判断できます。意味が通じる場合は「重文」、意味が通じない場合は「複文」です。
「日本語の文法は難しい!?外国人に教えるときに知っておきたいポイントを紹介」では、日本語の習得が難しい理由を言語的特徴を踏まえて解説しているので、参考にしてください。
日本語の文法【動詞】

動詞は、自然現象や状態のほか、人の行動、感情の変化などを表すときに使う品詞です。動詞は述語として機能する品詞であるため、意味や用法を理解しておきましょう。ここでは、動詞の活用や他動詞と自動詞の違い、時制について解説するので参考にしてください。
動詞の活用
動詞は、あとに続く言葉や文の意味によって「未然形(みぜんけい)」「連用形(れんようけい)」「終止形(しゅうしけい)」「連体形(れんたいけい)」「仮定形(かていけい)」「命令形(めいれいけい)」の6つの形に変化する品詞です。以下では、「書く」を例に6つの活用形と動詞に続く言葉・区切り符号、活用後の言葉を説明します。
| 活用形 | 活用形の意味や役割 | 活用後 | 動詞に続く言葉・区切り符号 |
| 未然形 | 打ち消しやまだ起こっていない 内容を表す際に使う活用形 |
書か 書こ |
「ない」 「う(よう)」など |
| 連用形 | 用言や助動詞に続く際の活用形 | 書き (書い) |
「ます」 「た」 |
| 終止形 | 文が終わるときや言い切る際に 使われる活用形 |
書く | 「。」 |
| 連体形 | 名詞に続くときの活用形 | 書く | 「とき」「こと」など |
| 仮定形 | 条件を仮定するときの活用形 | 書け | 「ば」 |
| 命令形 | 命令の意味で文を終わらせるときに 使う活用形 |
書け | 「。」 「!」 |
活用形を見分けるには、動詞の後に続く言葉を覚えておく必要があります。後に続く語から活用形を判断すると分かりやすいでしょう。アイウエオの5音で活用する五段活用の場合、終止形と命令形は、どちらも動詞の後に句点が続きます。活用後、終止形は「書くkaku」ウ段の音、命令形は「書けkake」エ段の音で終わると覚えておきましょう。
他動詞と自動詞の違い
動詞は、動作の対象を必要としない「自動詞」と、必要とする「他動詞」に分けられます。ここでは、「自動詞」と「他動詞」について解説。例文を参考に、自動詞と他動詞の違いについて理解しましょう。
【自動詞】目的語が必要ない(動作の対象を必要としない)
- 窓が開いた。
- 彼は笑った。
- 私は遊んだ。
【他動詞】目的語が必要。(動作の対象を必要とし、「~を」という対象を表す語がある)
- 私はご飯を食べた。
- 彼女は扉を閉めた。
- 彼はえんぴつを落とした。
「自動詞」と「他動詞」の区別がついていないと、正確な意味が伝わりません。たとえば、「落ちる」は自動詞で、「落とす」は他動詞です。男性がえんぴつを落とした様子を表現する際に、「自動詞」を使って「彼はえんぴつを落ちた」というのは間違っています。この場合は、「他動詞」を使い、「彼はえんぴつを落とした」とするのが正しい表現です。
時制の表現方法

日本語の時制には、「現在形」と「過去形」の2つの形があります。ここでは、動詞の時制について解説するので、参考にしてください。
【現在形】現在と未来を表現する際に使う
- 今、職場にいる。(動詞の現在形「いる」)
- これから家に帰る。(動詞の現在形「帰る」)
- 明日、遊園地に行く。(動詞の現在形「行く」)
【過去形】以前にあった内容を表す際に使う
- 昨日は学校に行った。(動詞「行く」の過去形「行った」)
- もう家に帰った。(動詞「帰る」の過去形「帰った」)
- 昨晩はたくさん勉強した。(動詞「勉強する」の過去形「勉強した」)
「現在形」で「今から」「これから」「明日」などの言葉が使われている場合は、未来の内容を表しています。未来の内容を表す際は「現在形」を使うので、覚えておきましょう。
日本語の文法【い形容詞・な形容詞】

日本語の文法上の品詞分類では、状態や性質を表すのが形容詞で、言い切りの形が「だ」で終わるものを形容動詞としています。日本語教育においては、形容詞を「い形容詞」と形容動詞を「な形容詞」と呼び、2つをまとめて「形容詞」と分類しているので、注意しましょう。
【い形容詞】
- 大きい、新しい、暑い、高い、おいしい、多い、軽い、広い、など
【な形容詞】
- きれいな、静かな、有名な、便利な、まじめな、心配な、大切な、など
い形容詞とな形容詞は、形容詞に続く名詞の前の語で見分けることができます。名詞の前が「い」であればい形容詞、「な」であれば、な形容詞です。「優しい人」は名詞である「人」の前が「い」なので、い形容詞です。「親切な人」は「人」の前が「な」なので、な形容詞と見分けられます。
日本語の文法【表現】

受け身や使役、授受動詞の意味と用法を理解しておくことは、自分と他者の行為を正確に表すうえで必要な知識といえるでしょう。ここでは、受け身や使役、授受動詞について解説します。動詞や助動詞の活用に注意して覚えましょう。
受け身
受け身とは、他から受ける動作のことです。自分の意志に関係なく、他者から受ける行為を表すときは、受け身文をつくります。
【例】
- 親に褒められる
- 先生に叱られた
受け身文は、動作の主体となる名詞に「に」または「を」の助詞をつけ、行為となる動作に助動詞「れる」「られる」をつけて文をつくります。
使役
使役とは、他者を使って行わせる動作のことです。使役の表現は、使役の助動詞である「せる」「させる」を使ってつくります。
【例】
- 子どもに片づけを手伝わせる
- 妹に荷物を運ばせる
- 息子にゲームをやめさせた
使役は「せる」「させる」のほか、助動詞「しめる」でも表せます。たとえば、事実を理解させるという場合は「彼女に事実を知らしめる」と表せるでしょう。
授受動詞
授受動詞は、他者と物をやり取りする際に使う動詞で「やりもらい動詞」とも呼ばれます。授受を表す際は、「あげる」「くれる」「もらう」という動詞を使います。「あげる」「くれる」「もらう」を使う際は、対象となる物がどこへ移動したのかに注意しましょう。自分から相手へ物が移動した場合は「あげる」、相手から自分に物が移動した場合は「もらう」または「くれる」を使います。
【例】
- 私は妹にお菓子をあげた
- 私は妹からお菓子をもらった
- 妹が私にお菓子をくれた
自分が主語のときは「もらう」を使い、他者が主語で自分が物を受け取った場合は「くれる」をつかいます。
難しいと感じる日本語については「日本語が難しいと感じる人が多い理由は?例文や勉強法を分かりやすく解説!」のコラムでも紹介しているので、参考にしてください。
日本語の文法【敬語】

日本語の敬語には、「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」があります。ビジネスシーンなどにおいては、敬語を頻繁に使用するため、マナーの一つとして覚えておきましょう。ここでは、敬語の種類と意味、用法について解説します。
丁寧語
「丁寧語」は、「です」「ます」など日常的な場面で使う機会が多い敬語です。相手や内容を問わず、丁寧に述べるときに使います。
尊敬語
「尊敬語」は、目上の人などに対して相手の行為を敬う際に使う敬語です。立場が上の人に対して、相手を立てるときに使います。また、相手の行為だけでなく、物事や状態に対しても使える敬語表現です。たとえば、住所を「御住所(ごじゅうしょ)」といったり、忙しいを「お忙しい」などと表現したりします。
謙譲語
「謙譲語」は、自分自身を下げて相手への敬意を表す敬語を指します。自分がへりくだることで、相手を立てて敬うという表現方法です。謙譲語は自分の行為を述べるときに使います。たとえば、自分が相手のところへ「行く」という行為を謙譲語では、「参る」「伺う」と表せるでしょう。
また、敬語は同じ言葉でも「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」のどれを使うかによって表現が異なります。たとえば、「言う」「食べる」を3つの敬語表現で言い換えた場合は、以下のとおりです。
- 「言う」
丁寧語:言います
尊敬語:おっしゃる、言われる、仰せになる
謙譲語:申す、申し上げる - 「食べる」
丁寧語:食べます
尊敬語:召し上がる、お食べになる、食べられる
謙譲語:いただく、頂戴する
敬語は、立場によって使い分ける必要があります。どの敬語表現を使うべきか迷ったときは、主語が誰であるかを考えると判断しやすいでしょう。
敬語について詳しく知りたい方は、「日本語の敬語の種類や使い方を外国人に向けて解説!」のコラムを参考にしてください。
改めてチェックしておきたい日本語の文法

日本語には、使い分けが難しい言葉や、独自の表現により意味が分かりにくい表現があります。ここでは難しい日本語表現について解説するので、参考にしてください。
擬音語と擬態語について
音や声を表す言葉を「擬音語(擬声語)」といい、人の様子や状態を表す言葉を「擬態語」といいます。擬音語と擬態語の例は、以下の通りです。
- 擬音語:「ワンワン(犬の鳴き声)」「コケコッコー(鶏の鳴き声)」「ザーザー(雨の音)」「ゴロゴロ(雷の音)」「ゴクゴク(飲み物を飲む音)」
- 擬声語:「イライラ(苛立っている様子)」「にこにこ(笑顔)」「わくわく(期待)」「ピカピカ(新しい物の様子・綺麗な状態)」
日本語の擬音語や擬態語は、日本人が独自に生み出した表現です。そのため、日本語学習者にとっては難しく感じることも。なお、擬音語と擬態語はまとめて「オノマトペ」ともいいます。日本語の会話や文章には多くのオノマトペが使われているので、よく使われる言葉の意味を覚えておきましょう。
「すぎる」の使い方

「すぎる」はプラスの意味でもマイナスの意味でも使われるため、意味を捉えるのが難しいと感じるときもあるでしょう。プラスの意味で使われている例文は、「美味しすぎる」や「楽しすぎる」などです。一方、「常識がなさすぎる」や「テストの点数が悪すぎる」などは、マイナスの意味で使われています。「すぎる」は、良くも悪くも普通以上であることを伝えたいときに使いましょう。
「こと」と「の」の使い分け
「こと」と「の」は同じ意味があり、言い換えられる場合がある言葉です。「歩くことは健康に良いでしょう」は、「歩くのは健康に良いでしょう」と言い換えられます。ただし、「です」や「だ」の前だと「の」が使えません。たとえば、「私の趣味は泳ぐことです」という文で「こと」を「の」に変えると、「私の趣味は泳ぐのです」となります。この場合は意味が通じないため、「の」に言い換えられません。
「ことがある」「ことはない」などの経験を表す文も、「の」は使えません。「約束する」「決める」などがあとに続く文の場合も、「の」に言い換えられないので注意しましょう。
対して、「聞こえる」や「見える」などの知覚動詞の前に「こと」は使えません。例文としては、「友達が歌っているのが聞こえる」「彼が手を振っているのが見える」などが挙げられます。
「こと」と「の」は、条件によって言い換えられない場合があると覚えておきましょう。
「くらい」と「ほど」の違い
「くらい」と「ほど」は、どちらも大体の程度を表すときに使います。例文として挙げられるのは、「1時間くらい本を読んだ」「動けないほど疲れた」などです。言葉の意味はほとんど同じで、より程度が高いときは「ほど」を使う場合が多いでしょう。
なお、「くらい」は最低限の状態・様子を表すときにも使えます。たとえば、「それくらい大丈夫でしょ」「お礼くらい言いなさい」などです。このような場合は、「くらい」を「ほど」に言い換えられません。
オノマトペについては「オノマトペとは?意味や使い方を覚えて表現を豊かにしよう」のコラムでも詳しく解説しているので、参考にしてください。
日本語の文法を理解するには

日本語の文法を学ぶには、日本の映画や本など、興味のあるものに触れると良いでしょう。ここでは、日本語の文法を学ぶ方法を3つ紹介します。
本やWebサイトの文章を読む

日本語の文法を学ぶには、本やWebサイトの文章を読むと良いでしょう。出版されている本や大手メディアのWebサイトは、プロが編集しているものです。そのため、正しい日本語の文法を身に付けるのに適しています。また、小説は独特な言い回しが多く使われているので、正しい文法に加えて新たな表現も学べるでしょう。
日本の映画やドラマを観る

日本の映画やドラマを観るのも、日本語の文法を学ぶ方法の一つです。日本の映画やドラマでは、日常的な場面で使う自然な会話を学ぶことができます。字幕や吹き替えを選べば、目と耳の両方で日本語を勉強できるのもメリットです。
また、最新の映画やドラマは、その作品が作られているときに流行っている言葉が使われます。そのため、日本の映画やドラマを観ると、若者言葉やSNSで流行っている言葉など、新しく生まれた単語を学ぶことも可能です。
分からない単語を辞書で調べる

日本語の文法を学ぶ際は、辞書を用意しておくのがおすすめです。本やWebサイトを読んでいる途中で、分からない単語や文章が出てくる場合があるでしょう。辞書で調べる習慣を付けると、疑問点を曖昧なままにせず解決できるため効率良く学べます。また、一度調べた単語は記憶に残りやすいこともメリットです。
日本語能力試験(JLPT)に挑戦する

日本語の文法を正しく理解するには、日本語能力試験(JLPT)に挑戦してみるのもおすすめです。日本語能力試験は、最も易しいN5レベルから段階的に難しくなっていくため、自分の能力に合ったレベルから受験できます。最も難しいレベルはN1レベルです。試験勉強を通して、日本語文法を理解し正しい知識を身に付けられるでしょう。また、進学や就職にも役立つ資格なので、挑戦してみてください。
日本語能力試験(JLPT)について詳しく知りたい方は、「【JLPT N5】日本語能力試験N5の受験方法や問題について解説!」のコラムを参考にしてください。
まとめ

日本語の文法とは、文章を構成するうえでの決まりや書き方のことです。正しい日本語の文法を使うには、ことばの単位や文節、品詞などを理解する必要があります。日本語の文法を正しく理解することはコミュニケーションに役立ち、自信にも繋がるでしょう。日本語を学ぶ方法はさまざまです。日本のドラマや映画を観たり日本語能力試験(JLPT)に挑戦したりして、正しい日本語を身に付けましょう。